

もうすぐ定年を迎えるけど、年金のみの収入や退職金の目減り、将来の介護費用などを考えると、老後生活に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、住宅ローンや医療費、子どもへの援助などが家計を圧迫し、年金だけでは生活がままならず老後破産になる高齢者も少なくありません。
今回は、老後破産の特徴や原因、今からできる対策について分かりやすく解説しつつ、老後破産になっても介護を受ける際に利用できる制度と相談先をご紹介します。
老後破産を未然に防ぎ、安心して老後生活を送るためのヒントが見つかるため、ぜひ最後までご覧ください。
老後破産とは?増加する背景と実情を解説


老後破産とは、年金収入だけでは生活がままならず家計が破綻した状態のことで、近年では60歳以上の高齢者が自己破産するケースが年々増えています。
こちらでは、老後破産の背景や実態について解説します。
老後破産とは?
老後破産とは、老後の生活において、年金収入だけでは生活費や医療費をまかなえず、家計が破綻してしまう状態のことです。
定年退職後は年金が主な収入源になりますが、支出は思いのほか増える場合があります。
たとえば、貯蓄が不十分な場合、退職金を使い切ってしまい、家計が赤字へ傾いてしまうケースも珍しくありません。
実際、老後破産によって生活苦となり、やむを得ず生活保護を頼る人も増えています。
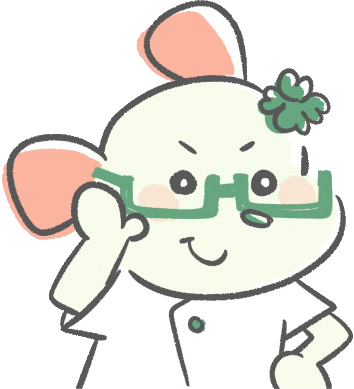
老後破産の実態と割合
老後破産は、一部の人に限った話ではありません。
実際、破産債務者の約4人に1人が60歳以上であるというデータもあります。
日本弁護士連合会「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、60代が16.3%、70代以上が9.3%となっており、年を追うごとに増加傾向となっています。
また、厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和5年度)」によると、生活保護を受けている世帯の半数以上が高齢者世帯で、その9割が単身の高齢世帯であることも判明しています。
さらに、総務省「家計調査報告(令和6年度)」でも、高齢単身・夫婦世帯ともに毎月の支出が実収入を上回り、月に数万円の赤字になっていることも発表されています。
このような実態から、老後破産は「想定外」ではなく、誰にでも起こりうる身近なリスクと言えるでしょう。
老後破産になるとどうなるの?
老後破産をすると、自宅や車といった資産を手放すことになり、生活水準が一気に下がる可能性があります。
たとえば、公共料金の滞納によって電気・ガスが止められることや必要な医療・介護が受けられないなど、生活の基盤が大きく揺らぐ場合もあります。
また、自己破産をすると、原則として持ち家などの財産は処分され、それでも生活が成り立たない場合は生活保護の申請も考えなければなりません。
年金や最低限の生活必需品は守られるとはいえ、十分な収入がなければ最低限の生活を維持することは難しいでしょう。
老後破産になりやすい人の4つの特徴


老後破産になりやすい人には、以下の4つの共通した特徴があります。
- 住宅ローンを定年前に完済できていない
- 退職金を一気に使ってしまう
- 年金収入に頼り切っている
- 介護や医療など将来の備えがない
一つずつ解説します。
住宅ローンを定年前に完済できていない
老後破産を招きやすい人の特徴の一つが、定年前に住宅ローンを完済できていないことです。
定年後は収入が年金だけに限られるため、毎月のローン返済が続くと、家計はすぐに赤字となるでしょう。
日本弁護士連合会「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、住宅を所有する債務者のうち、個人再生を選ぶ割合は37.88%と、自己破産(3.47%)よりも高く、返済の重さが伺えます。
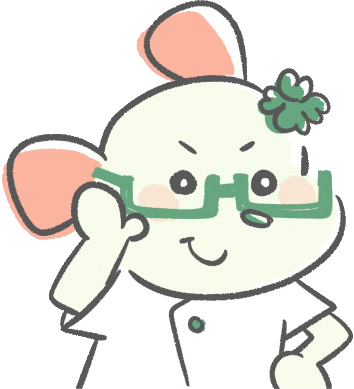
退職金を一気に使ってしまう
退職金を一気に使ってしまう人も、老後破産を招きやすい特徴のひとつです。
例えば、定年後の収入源が年金だけの場合、現役時代の生活レベルを維持し続けると、支出のバランスが崩れて赤字となり、退職金はあっという間に底をつきます。
特に、高リスクな投資で損失を出してしまった場合や生活水準を見直さないまま使い続けた場合、資金不足に陥り、老後破産に向かうリスクが高まります。
退職金は老後を支える重要な資金であるため、慎重に使い道を計画しましょう。
年金収入に頼り切っている
年金だけに頼る生活は、医療費や生活費の増加に対応しきれず、慢性的な赤字になるリスクが高いです。
厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均受給月額は約14万円となっており、夫婦2人でも十分な生活費を賄うことは難しいです。
また、単身世帯や扶養中の人、自営業者は年金額がさらに低いため、特に老後破産に陥るリスクが高いとされています。
このような状況から、定年後も収入を得られるように再雇用や資産形成などで収入の柱を増やし、年金収入だけに頼らない生活設計が重要です。
介護や医療など将来の備えがない
介護や医療への備えがないことも、老後破産を招きやすい人の特徴です。
高齢になると、病気や介護が必要となるリスクが高まり、入院費や介護施設の利用料など、予想外の出費が発生する場合もあります
例えば、何も準備をせずに老老介護に直面すると、医療費や介護費用がふくらみ、生活が立ち行かなくなるケースも少なくありません。
公的制度の利用や民間保険への加入、貯蓄による費用の確保を早めに行うことによって、安心して老後を迎えることにつながるでしょう。
老後破産を招く5つの原因


老後破産を招く原因には、以下の5つの原因が挙げられます。
- 生活費の見積もりが甘い
- 医療費・介護費が急に増えている
- 収入が減り、支出が増えている
- 子どもへの援助や教育費で資産を使い果たしている
- 熟年離婚や夫婦関係が悪化している
くわしく解説します。
生活費の見積もりが甘い
老後破産を招く原因のひとつが、生活費の見積もりが甘いことです。
厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」では、ひと月あたりの厚生年金の平均月額は約14万円となっており、高齢の夫婦が生活するには心もとない金額と言えます。
現役時代の生活レベルを変えられず同じ程度の支出が続くと、年金だけでは賄いきれないため慢性的な赤字が続き、すぐに貯蓄は底をつくでしょう。
そのため、定年後の支出を想定し、早めに家計を見直すことが、老後破産を防ぐための備えとなるでしょう。
医療費・介護費が急に増える
医療費や介護費の急な増加は、老後破産につながる可能性が高いです。
高齢になると、病気の治療や入院、介護サービスの利用が避けられず、多額の出費が発生するリスクがあります。
例えば、有料老人ホームへの入居には、入居一時金や月額利用料で数百万円〜数千万円が必要なケースもあります。
また、高齢者の医療費は現役世代より安い傾向ですが、病気によっては長期的な治療が必要となり、結果的に医療費は高くつくケースも少なくありません。
こうした事態に備えて、医療・介護にかかる支出を事前に把握し、資金計画を立てることで、安心した老後生活につながるでしょう。
老人ホームなどの介護費用が気になる方は、こちらの記事もおすすめです。
収入が減り、支出が増えている
年金収入だけの生活になると、現役時代と同じ水準で生活できず、家計が赤字に変わるリスクがあります。
厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均月額は約14万円と発表されています。
また、総務省「家計調査報告(令和6年度)」では、夫婦2人暮らしでも支出が収入を上回っていることが判明しています。
このような収支のギャップは深刻となっており、さらに物価上昇や医療・介護費の増加も追い打ちをかけているため、老後破産になるリスクが高いです。
そのため、生活水準を見直し、「毎月いくらで生活できるか」をシミュレーションすることが、安心した老後生活を築く第一歩となるでしょう。
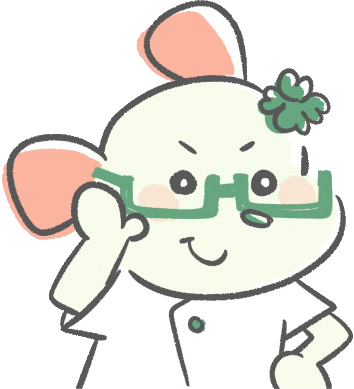
老後の生活に必要な資金について知りたい人は、こちらの記事もおすすめです。
子どもへの援助や教育費で資産を使い果たしている
子どもの学費や生活費を援助し続けることで、老後の資金を想定よりも早めに使い果たすリスクが高いです。
晩婚化の影響もあり、定年後も学費の支払いや仕送りが続く家庭では、年間100万円以上の支出になることも珍しくありません。
さらに、自立しきれない子どもに援助を続けることで、将来的に家計が破綻するリスクが高まります。
もちろん親心としてはサポートしてあげたい気持ちは理解できますが、老後の資金は自分たちの人生の大きな土台になります。
子どもへの支援の限度や優先順位を夫婦間であらかじめ話し合い、「どこまで支援するか」というラインをはっきりすることが必要と言えるでしょう。
熟年離婚や夫婦関係が悪化している
熟年離婚や夫婦関係の悪化は、老後資金の大幅な減少や生活費の負担増を招き、老後破産のリスクを高める要因になるでしょう。
離婚による財産分与や年金分割によって年金受給額が減ることもあり、特に一人暮らしとなった場合、生活費のやりくりが一気に厳しくなります。
実際に、離婚後に生活が困窮し、生活保護を頼る高齢者も少なくありません。
こうした事態を防ぐには、夫婦関係が良好である間に「お金」「将来の住まい」「相続」などについて定期的に話し合い、資産管理を共有することが大切です。
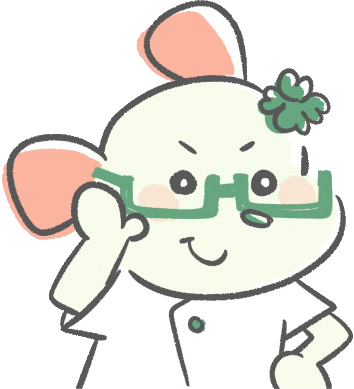
老後破産を防ぐために今すぐできる5つの対策


老後破産を未然に防ぐためには、以下の5つの方法を基に、早めに手を打つことが重要です。
- 家計を見直す
- 住宅ローンを完済する計画を立てる
- 退職金の使い方を計画する
- 定年後も働くことを考えておく
- 不動産などの資産を活用する
くわしく解説します。
家計を見直す
老後破産を防ぐためには、日々の家計を見直すことです。
特に通信費や保険料、サブスクなどの固定費の見直しは効果が大きく、毎月の支出を大きく抑えることができます。
たとえば格安スマホへの乗り換えや、不要なサブスクの解約、保険の見直しで月数千円〜数万円の節約も可能です。
また、日々の買い物では、まとめ買いや自炊の習慣化、光熱費では節電・節水を意識することで、無駄な支出を防ぐことにつながります。
老後の家計を安定させるには、現役時代の支出習慣をそのまま引き継がないことが大切であるため、無駄を見直し、老後破産のリスクに備えましょう。
住宅ローンを完済する計画を立てる
住宅ローンが老後まで残っていると、年金だけで生活費と返済を賄わなければならないため、結果的に老後破産に陥るケースも少なくありません。
そのため、定年退職前までにローンを完済できるよう計画を立てることが必要です。
しかし、早期完済を目指す場合、貯蓄が枯渇しないように返済と貯蓄のバランスには注意しましょう。
また、ローン残債のある持ち家を売却し、賃貸に住み替える方法も選択肢の一つです。
ローンの有無は老後の家計に影響を与えるため、今のうちに返済シミュレーションを行い、確実に完済できるようスケジュールを立てることが重要です。
退職金の使い方を計画する
退職金は老後の生活を支える大切な収入源ですが、無計画に使うとあっという間に底をつく可能性があります。
たとえば、家のリフォームや子どもへの援助、高額な買い物を繰り返してしまうと、必要な生活費や医療費が足りなくなるリスクもあります。
そのため、退職金は生活費や医療・介護費、緊急予備費など、使い道を明確にしましょう。
また、必要に応じてファイナンシャルプランナーに相談し、適切な配分を決めておくと、より安心できるでしょう。
退職金をしっかり管理すると、将来の不安を減らし、安心して老後の生活を過ごすことにつながります。
定年後も働くことを考える
年金収入だけでは生活が成り立たず、退職金も尽きると老後破産のリスクは高まります。
そのため、定年後も働き続ける方法も老後破産を防ぐ方法の一つです。
近年では、老後も無理なく働ける選択肢として、以下の4つ方法で働くことができます。
- 勤めている職場での再雇用
- シルバー人材センター
- 副業
- 在宅ワーク
また、ある程度の収入があると、年金の繰下げ受給で将来の年金額を増やすことも可能です。
少しでも稼げる仕組みを作ることで、生活費の補填や貯蓄の温存につながり、精神的な余裕にもつながります。
定年後の働き方は、安心した老後の生活を左右する重要なカギとなるでしょう。
老後も働いて収入を得たい人は、こちらの記事もおすすめです。
不動産などの資産を活用する
所有している不動産などの資産を活用する方法も、老後破産を防ぐことにつながります。
たとえば、自宅を売却して住み続けられるリースバックや自宅を担保に融資を受けるリバースモーゲージを活用すると、まとまった資金を得ることができます。
また、使っていない土地や空き部屋を賃貸に出すことで、安定した賃貸収入を得ることも可能です。
しかし、高齢になるほど資産の売却や運用する判断が難しくなるため、早めに準備することが重要です。
眠っている資産を収入源に変えることは、老後の生活費や医療費の不安を解消し、穏やかに生活することができるでしょう。
しかし、不動産などの資産活用にはさまざまなトラブルを伴うリスクもあるため、以下の記事もあわせてご覧ください。
老後破産しても介護は受けられる?生活保護・負担軽減制度・相談先を紹介


万が一、老後破産になってもさまざまな制度を利用しながら介護サービスを利用することができます。
ただし、制度を利用するためには条件が伴うため、まずは各種窓口で相談しましょう。
こちらでは、老後破産の状態で介護を受ける際に利用できる制度と相談窓口について解説します。
介護費に関する負担軽減制度を利用する
介護サービスを利用すると、自己負担額が家計を圧迫し、老後破産のリスクを高める場合もあります。
そのため、介護費に関する負担軽減制度を利用することも重要なポイントです。
たとえば高額介護サービス費制度は、1ヶ月あたりの自己負担額の上限を超えた分を払い戻すことができます。
また、負担限度額認定を受けると、介護施設やショートステイ入所時の食費・居住費を軽減することが可能です。
しかし、いずれの制度も収入や資産に応じて適用されるため、まずは市区町村の窓口で相談しましょう
制度を正しく理解して活用すると、無理のない範囲で安心して介護サービスを利用できます。
よりくわしい負担軽減制度を知りたい人は、こちらの記事もおすすめです。
生活保護の受給を検討する
経済的に厳しい状況が続き、介護費や医療費を支払えない場合は、生活保護の受給を考えることも選択肢の一つです。
生活保護には、生活扶助・住宅扶助・介護扶助などがあり、介護が必要な高齢者でも支援を受けられる仕組みとなっています。
また、年金受給者であっても、収入や資産が一定の基準より下回っている場合、生活保護の対象となる可能性があります。
「資産をすべて手放さないといけない」と誤解されることもありますが、生活を維持するための最低限の資産を持つことは認められています。
生活保護は最後の手段ではなく、安心して老後生活を送るためのセーフティーネットとして利用できるため、まずは各市区町村の窓口に相談しましょう。
介護が必要になった時相談できる3つの窓口
介護が必要になったとき、一人で抱え込まずに相談することも大切です。
特に、以下の3つの窓口では、介護に関する相談や生活支援に関するさまざまなサポートを受けることができます。
- 地域包括支援センター
- 市区町村の窓口
- 社会福祉協議会
また、経済的に厳しいけど老人ホームへの入居を考えたい方は、地域介護相談センター「近所のよしみ」へ相談することもおすすめです。
国家資格を取得し、介護現場を経験したプロのスタッフが、現在の状況やご希望に合わせた施設選びから入居までサポートします。
また、老後破産によって生活が困窮している方や生活保護を受給されている方は、必要に応じて役所の担当課と調整し、入居できる施設の提案などのサポートにも対応します。
老後になると介護の不安はいつもつきまとうため、ご紹介した窓口へ相談することで、介護の不安を解消し、安心した老後生活を送ることにつながるでしょう。
まとめ
老後破産は、年金収入だけでは生活費や医療・介護費をまかなえず、家計が破綻してしまう状態を指します。
主な原因には、住宅ローンや退職金の使い方、将来の介護費用の備えが不十分なことが挙げられます。
老後破産を防ぐためには、以下の5つの対策を行うことが重要です。
- 家計の見直し
- 住宅ローンの完済を計画する
- 退職金の使い方を計画する
- 定年後も働くことを考える
- 不動産などの資産を活用する
万が一、老後破産になっても、公的な介護費の負担軽減制度・生活保護を利用し、介護サービスを利用できます。
ただし、制度の利用には条件が伴うため、まずは地域包括支援センター・市区町村の窓口・社会福祉協議会へ相談することをおすすめします。
老後破産を防ぎ、安心して老後生活を迎えることができるよう早めに行動しましょう。




















