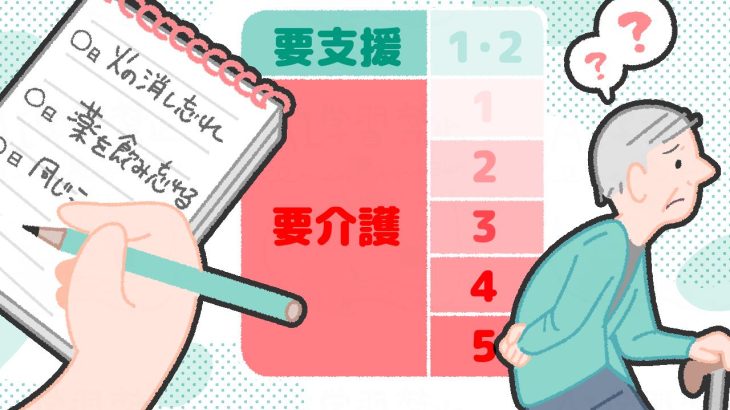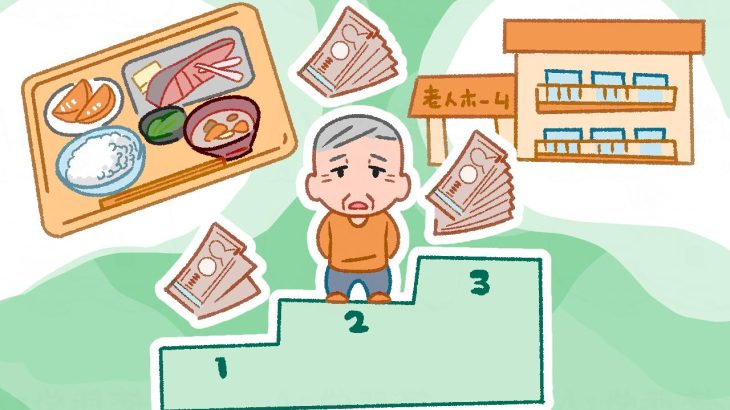このように思われている方いるのではないでしょうか。
その症状、尿路感染症かもしれません。
尿路感染症は高齢者が熱を出す原因でとても多い病気と言われています。
高齢者は免疫力の低さから感染症になりやすいと言われており、「肺炎」の次に多いのが「尿路感染症」なんです。

尿路感染症とは
尿路感染症は何らかの病原体(主に細菌)の感染により、尿道から腎臓までの尿路に起こる感染症の総称です。
それぞれの部位により病名が変わり、膀胱なら「膀胱炎」、腎臓なら「腎盂腎炎」と呼ばれています。細菌が尿の出る入り口から入り込み、感染が起きることが多い病気です。


高齢者が尿路感染症になりやすい理由
ではなぜ高齢者は尿路感染症になりやすいと言われているのでしょうか。1つずつ見ていきましょう。
排尿を我慢してしまう
認知症があり尿意が曖昧であったり、活動量の低下や四肢麻痺があり体が思うように動かせないなど、尿意があっても我慢をしてしまうことなどがあります。
このようなことにより、膀胱内に長時間尿がたまると、細菌が繁殖しやすく、膀胱炎になりやすくなるため注意が必要です。

水分摂取量が少ない
高齢者は水分摂取量が低下しがちです。
その理由は活動量が少なくのどが乾かない、おしっこにすぐに行きたくなるのは困るから水分はあえてとらない、認知症があり、食事や水分摂取を拒否するなどさまざまです。すると排尿量が少なくなり、膀胱内で尿を貯める時間が長くなり、その結果細菌が繁殖していきます。

陰部が清潔に保たれていない
オムツの使用や、便尿失禁などで陰部が汚染されている時間が長いと、尿の出る入り口から細菌が入り込み感染を起こす可能性があります。
排尿障害がある
尿をスムーズに出す、貯めるなどの機能がうまくいかない排尿障害をもっていると、尿が停滞し、細菌が繁殖しやすい状態と言われています。
以下は排尿障害を起こす病気の一例で、高齢者に多い病気です。
- 前立腺肥大症
- 前立腺がん
- 神経因性膀胱
- 尿管結石症
感染しやすい状態である
高齢者は加齢に伴い、免疫機能が低下します。それに加え糖尿病や脳血管障害、動脈硬化など元の病気を持っていると、より感染しやすい状態になります。

尿路感染症の種類と症状
ここでは尿路感染症で特に多い膀胱炎、腎盂腎炎の種類や症状をみていきましょう。
単純性(急性)膀胱炎
泌尿器系や全身の病気をもっていない場合に起こる膀胱炎です。
尿道の長さが短い女性に多いのが特徴といえます。
複雑性(慢性)膀胱炎
泌尿器系や全身の病気を持っている場合に起こるものです。
排尿障害により、尿が停滞し感染を起こすと言われています。元の病気があるため再発を起こしやすく慢性化しやすいのが特徴です。
膀胱炎の症状

単純性(急性)腎盂腎炎
泌尿器系や全身の病気をもっていない場合に起こる腎盂腎炎です。
軽症~重症まであり、細菌が血液内に入ると敗血性ショックを起こす可能性もあるため注意が必要です。
複雑性(慢性)腎盂腎炎
泌尿器系や全身の病気を持っている場合に起こります。
元の病気があるため、再発を繰り返し、慢性化していくことで腎機能が徐々に低下していきます。
単純性と同じく、敗血性ショックを起こす可能性もあるため、注意しましょう。
腎盂腎炎の症状
発熱、頻尿(1日8回以上の排尿)、悪心、嘔吐、腰や背中の痛み、排尿時の痛み、腎機能障害、ショックの可能性


尿路感染症の治療
抗生物質による治療
尿路感染症の症状は軽症から重症まであり、抗生物質の内服で治療できるものから、入院し点滴を行う場合まであります。
また抗生物質にはさまざまな種類があり、原因となる細菌によく効くものを選ぶことが重要です。「尿培養」といい、尿中の細菌の種類や量をみて、抗生物質の種類を決め、治療していきます。
高齢者の場合、抗生物質による耐性があり、多くの薬が効きにくくなる場合もあるので注意が必要です。
原因となる病気の検査と治療
元の病気がある場合、熱が下がりづらく、1度治っても再発しやすい状況です。
前立腺肥大症や尿管結石症など原因となる病気がある場合、腹部エコーやCT検査が行える医療機関へ行き、今の状態を見てもらいましょう。場合によっては外科的処置が必要な場合もあるので早めの受診が必要です。


尿路感染症かもと思ったらチェックするべきこと
- オムツ内は清潔に保たれているか
- オムツが汚れていることに気づいているか
- 陰部の皮膚の状態はよいか
- 尿意があっても我慢していないか(トイレの場所が分からない、また介助者に申し訳なくて黙っているなど)
- トイレの回数は多すぎないか(8回以上は頻尿と呼ぶ)
- 排尿する時間は長すぎないか
- 排尿時痛みはないか
- 尿の濁り、匂いが普段よりきつくないか
- お腹の痛みはないか
- 尿が残ってる感じはないか
- 腰、背部の痛みはないか
- 発熱していないか
- 食事、水分はとれているのか
- 睡眠はとれているのか

尿路感染症への援助と予防
適切なトイレ援助する
認知症などで尿意があいまいな場合は時間を決め、トイレ誘導を行いましょう。
場所が分からず、困っている場合はトイレの場所を分かりやすく提示します。
四肢麻痺で歩行状態や排尿動作が不安定な場合は近くにポータブルトイレを設置することでスムーズに排尿出来るかもしれません。

オムツ内清潔を保持する
オムツを使用する際はサイズや種類、吸収力など目的に合わせてオムツを選びます。
排尿・排便の量や性状は人によりさまざまなので、その方に合わせてオムツ交換をしましょう。尿意がしっかりしている場合はオムツではなく採尿器を使用すると、ベット上でも排尿できるため、検討してみてください。

水分は多めに摂取する
水分は出来るだけ普段より多めに飲みましょう。一度にたくさんの量を飲むことは大変なので、細めに分割して飲むことをお勧めします(朝食時・10時・昼食時・15時・夕食時など)。
水分を多めに飲むことで、尿量を増やし細菌を薄め、洗い流す効果があります。

下腹部を冷やさない
下腹部を冷やさないよう注意しましょう。下腹部を温めることで、膀胱内の血流がよくなり、細菌が入りにくく免疫が上がると言われています。
内服薬は確実に飲む
病院からもらった内服薬は必ず飲むようにしましょう。症状が収まっていても、決められた量、決められた期間飲みます。
元の病気の薬もあれば、継続的に飲んでください。
まとめ
高齢者の尿路感染症は、原因となる病気があることで、再発しやすく慢性化するといわれています。繰り返される発熱や不快な症状は日常生活に大きく支障をきたしますよね。
か少しでも気になることがあれば、早めに受診して、医師の診察を受けましょう。
早めに予防し、治療につなげることが大切です。
参考文献
- https://www.microbio.med.saga-u.ac.jp/Lecture/kohashi-inf4/part5/5g1.html
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jahcm/6/1/6_6.1_1/_pdf
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/resja/36/4/36_211/_pdf/-char/ja
- https://www.microbio.med.saga-u.ac.jp/Lecture/kohashi-inf4/part5/5g3.html
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/47/6/47_6_565/_pdf
- https://www.hosp.kagoshima-u.ac.jp/ict/koukinyaku/nyourokansensyou.htm