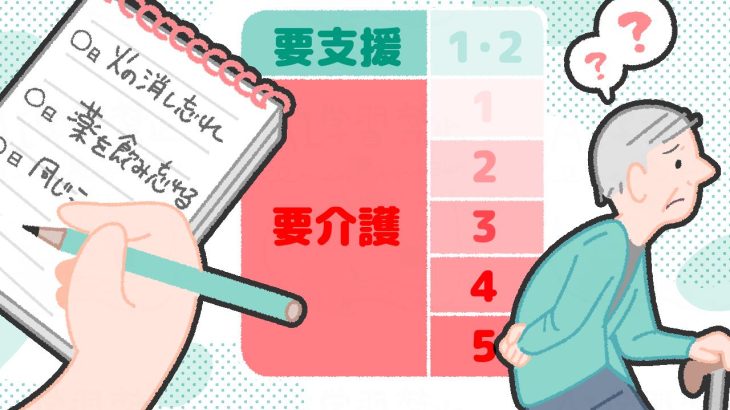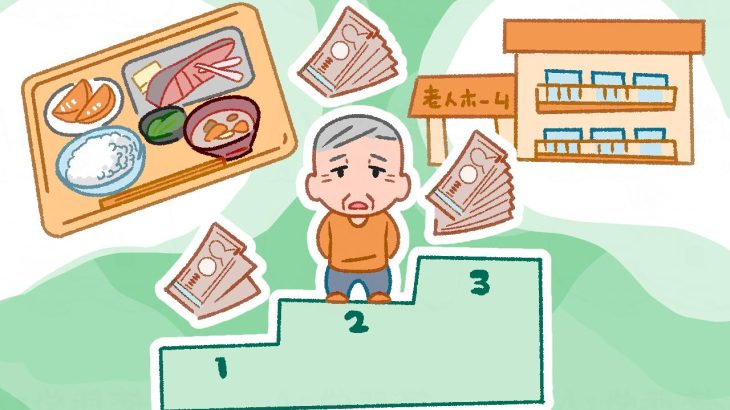―有料老人ホームの昼食どきのことです。





誤嚥性肺炎とは
「誤嚥」(ごえん)とは、加齢や病気によって飲み込む機能(嚥下力)が衰えることで、飲食物や唾液が誤って気管に入ってしまうこと
気管に入った飲食物や唾液の中に含まれる細菌から肺炎が起こる病気を誤嚥性肺炎と言います。
高齢者の肺炎の7割は誤嚥性肺炎です。肺炎は日本人の死因の上位に入っており、これは長生きをする高齢者の割合が増加したためと考えられます。
誤嚥性肺炎の原因
- 飲み込みがうまくできない
- 胃食道の逆流:寝ている時や横になった時に胃内容物が逆流し、気管に流れ込む
- 水分を制限をする:脱水になり唾液量が減少、食べ物がのどに残りやすい
- 義歯の不具合、歯の弱り:噛むことと飲み込みに支障が出る
- 口や舌の筋力低下:舌の動きが悪くなり、食べ物を喉の奥へ送り込むことに支障が出る
- のどの筋力や反射の低下:誤嚥時に咳き込まない、または咳込みが弱い
- 常用している薬の影響:副作用により口腔乾燥や筋力低下、咳反射が低下する薬がある
- 病気そのものの影響:パーキンソン病や脳卒中など

誤嚥性肺炎の初期症状
初期症状は風邪の症状によく似ている
受診したとしても風邪と診断されることがあります。
診てもらう時にはむせやすくなったことなど、摂食嚥下障害があれば一緒に伝えましょう。
- なんとなく元気がない
- 体がだるく、疲れやすい
- 寒気(悪寒)、発熱:37.5℃以上
- 激しい咳と黄色や緑色の痰
- 呼吸がつらい、息苦しい

認知症との関係性
認知症では食べ物を口に入れる前や入れた後に、それがなにかを正しく認識することが難しくなることがあります。
症状がわかりやすい以下の2つで説明します。
- アルツハイマー型認知症:目の前の食事を『食物』と認識できずに食事を始めることができない。低栄養になってしまう。
- レビー小体型認知症:身体機能が低下するため、飲み込み動作も徐々に難しくなる。食物を飲み込めないために口の中にたまりむせてしまう。
最近では、サルコペニア(※)によって食べるために使う筋肉量が減り、食べる機能が低下していることも原因の1つとされています。
※サルコペニア:加齢や不活発な生活、原疾患や低栄養が原因で筋肉量が減少し筋力や身体能力が低下した状態のこと。
このような状態が続くといずれ誤嚥性肺炎を起こす可能性が高くなります。
嚥下機能チェック
現在の飲み込みの機能がどれくらいか、一緒にチェックしてみましょう。
嚥下障害を自分でチェック
- 食事中にむせることがある
- 唾液が口の中にたまりよだれが出る
- 飲み込むことに苦労することがある
- 硬いものが噛みにくくなった
- 舌に白いコケのようなものがついている
- 声が変わった(ガラガラ声)
- よく咳をする
- 食事を残すことが多い(食べる量が減った)
- 体重が減った(1ヶ月で5%以上、半年で10%以上)
このような症状が1つでもあったら嚥下障害を疑います。

のど年齢チェック
簡易的な飲み込みのテスト『ごっくんテスト』です。
準備するもの:少量の水
- 水を1口飲み、口の中を湿らせる。
- 自分の手をのど仏にあて、30秒で何回唾液を飲み込めるかを数える。

のど年齢
- 8回飲み込めた:40歳代
- 7回:50歳代
- 6回:60歳代
- 5回:70歳代
- 4回以下:80歳以上


誤嚥性肺炎の予防トレーニング
予防トレーニングにはいくつかの方法があります。今回は簡単にできる『パタカラ体操』『あいうべ体操』『のど仏トレーニング』をしてみましょう。
まずは準備体操です。
- 深呼吸をゆっくりと数回行う
- 首をゆっくり前後左右に倒す。首を回す(首に病気や痛みなどがある方は、首のストレッチをしない)。数回繰り返す。
パタカラ体操
口の周りや舌の筋肉のトレーニングです。
1音につき5秒程度「パ・パ・パ」、「タ・タ・タ」、「カ・カ・カ」、「ラ・ラ・ラ」と繰り返して発声します。
- パ:唇の筋肉で食べこぼしを防ぐ
- タ:舌の筋肉で食べ物を喉まで動かす
- カ:のどの奥を閉じるトレーニング
- ラ:舌の筋肉で食べ物を口からのどに運ぶ
10回ずつ発音し、5回繰り返して行ってみましょう

あいうべ体操
口を大げさに動かし発声します。
- あ〜:口をたてに大きく開く
- い〜:口を思い切り横に開く
- う〜:唇をとがらせて思い切り前に突き出す
- べ〜:下顎に舌の先をつけるイメージで長くのばす
「あ〜い〜う〜べ〜」をそれぞれ1秒間ずつ、5回繰り返してみましょう。

のど仏トレーニング
のど仏を動かす筋力が低下すると飲み込むための反射が弱くなる
のど仏に手を当て唾液を飲み込んでみてください。
のど仏が上にあがる時に食道の入り口が広がり、気管の入り口が閉じられます。この動きが不十分だと誤嚥する可能性が高まります。
- のど仏に手を当てる
- 低い声で「オー」と発声する
- 次に甲高い声で「ヒー」と発声する
- この繰り返しを1日10回行う。

口腔ケアで誤嚥性肺炎予防
お口のケアは細菌の繁殖をおさえ、虫歯と歯周病も予防します。
口の中の細菌のとり方
歯に付着しているネバネバしたバイオフィルム(細菌の膜)や歯垢を歯ブラシでこすり落としましょう。
- 歯ブラシ以外のデンタルフロスや舌ブラシも使う:奥歯はブラシが届きにくい
- 毎食後に歯磨きを行う:食後8時間ほどで歯垢は形成される
- 歯磨き回数は毎食後と起床してすぐ、就寝前の5回が理想
- ブラシはふつう〜やわらかめを使う
歯科で定期的にクリーニングをしてもらいましょう
まとめ
誤嚥性肺炎は高齢者に多く見られる疾患で、加齢や疾患による嚥下機能の低下が主な原因です。初期症状は風邪に似ており、むせる、痰が増える、食欲低下などの前兆に注意が必要です。
認知症患者は特に発症リスクが高く、「ごっくんテスト」で自身の嚥下機能をチェックできます。
予防には「パタカラ体操」「あいうべ体操」「のど仏トレーニング」などの簡単な口腔トレーニングが効果的で、毎食後の丁寧な歯磨きなど口腔ケアも重要です。これらの対策を日常生活に取り入れることで、誤嚥性肺炎のリスクを減らし、健康的な生活を維持できます。
飲み込む力は食事を美味しく十分に摂る力とも言えます。簡単にできるチェック方法やトレーニングで飲み込む力を保ちましょう。そして健康寿命をのばして毎日を楽しく過ごせたらいいですね。