

熟年再婚は実の親にとって大切な人生の再出発ですが、場合によっては相続トラブルの火種になることもあります。
特に、再婚相手に連れ子がいる場合や遺言がない場合、相続権や相続配分などを巡り、思わぬ争いに発展するケースも少なくありません。
今回は、熟年再婚による相続トラブルの背景や内容、トラブルを未然に防ぐ対策について、分かりやすく解説します。
併せて、熟年再婚による介護施設の入所や老後の暮らしに与える影響についても解説します。
こちらの記事を読むことで、熟年再婚による相続トラブルや介護が必要になった際のトラブルを防ぐためのヒントを得ることができるでしょう。
「親が再婚したけど、今後の相続や老後の生活が心配…」と感じている方は、ぜひご覧ください。
熟年再婚による相続トラブルが増えている3つの背景


と気になる方も多いのではないでしょうか。
実際、以下の3つの背景によって、熟年再婚による相続トラブルが増えており、頭を抱える方が多くいます。
- 複雑な家庭環境によって相続人の利害が対立する
- 実の子どもと再婚相手の感情的に対立が生まれやすい
- 相続に関する準備不足がトラブルの原因になる
詳しく解説します。
複雑な家族関係によって相続人の利害が対立する
熟年再婚では、相続人同士の利害がぶつかりやすく、深刻な相続トラブルにつながることがあります。
再婚によって相続人の構成が複雑になり、実の子・再婚相手・連れ子が相続権を持つ場合があるからです。
たとえば、実の子は「親の財産は自分たちで築いたもの」と考える一方、再婚相手も「夫婦として過ごした分の権利がある」と、お互いの考えがぶつかりトラブルに発展することもあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、あらかじめ家族の考えと相続配分などを明確にしておくことが必要です。
実の子と再婚相手の感情的に対立が生まれやすい
熟年再婚では、実の子と再婚相手の間に感情的な対立も生まれやすいです。
実の子と再婚相手との間で信頼関係が築けないまま、相続というデリケートな問題に向き合わないといけないためです。
たとえば、再婚相手が親の財産を相続することで、実の子が「財産目当ての再婚では?」と疑念を抱き、次第に感情的な対立へと発展する場合があります。
このようなすれ違いや不信感が積み重なり、感情的な対立が深まり、結果的に相続トラブルにつながります。
相続に関する準備不足がトラブルの原因になる
相続に関する準備不足は、熟年再婚における相続トラブルの大きな原因になります。
特に、遺言書を作成していない場合、誰にどの財産を相続するのか明確ではないため、残された家族の間での争いの火種となります。
また、再婚や相続について話し合う機会がないと、誤解や不信感を招き、結果的に相続トラブルへ発展する場合もあります。
そのため、事前に専門家への相談・遺言書の作成などの対策を早めに準備することが大切です。
熟年再婚をすると、相続人と相続の割合はどうなる?


実の親が熟年再婚すると、相続人の範囲と相続の割合が変わるためしっかり理解することが必要です。
こちらでは、熟年再婚の場合に考えられる相続人と相続割合の違いを、次の3つのケースに分けてわかりやすく解説します。
- 実の子のみが相続人になる場合
- 再婚相手と実の子が相続人になる場合
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合
相続の仕組みについて気になる方は参考にしてください。
実の子のみが相続人になる場合
親が熟年再婚をしても、再婚相手がすでにいない場合は相続人は実の子だけです。
法律上、実の子は最も優先される第1順位の相続人と定められており、相続の権利が確実に守られています。
たとえば、実の子が2人いる場合は遺産は2分の1ずつ、3人なら3分の1ずつ均等に分けられます。
また、性別や結婚などに関係なく、実の子であれば同じ権利を持っており、遺留分として最低限でも遺産の半分は必ず受け取ることが保証されています。
このように、すでに再婚相手がいない場合、相続は実の子だけで行われるため、相続トラブルは起こりにくいと言えるでしょう。
再婚相手と実の子が相続人になる場合
再婚相手と実の子が相続人になる場合、相続の割合は大きく変化します。
法律上、配偶者が常に法定相続人と定められているため、再婚相手であっても相続人としての権利は変わりません。
たとえば、実の子が1人の場合、再婚相手・実の子ともに2分の1ずつですが、実の子が2人の場合、再婚相手は2分の1ですが、実の子は残りの2分の1を均等に分けなければなりません。
このような配分によって「再婚相手に多く相続される」と感じた実の子が不満を抱く場合もあります。
相続トラブルを防ぐには、再婚相手と実の子が納得できる形で相続ができるように事前に家族全員で話し合いましょう。
再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合
再婚相手の連れ子と実の親が養子縁組をした場合、相続においては実の子と同じ立場になります。
連れ子と実の親が養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立するため、熟年再婚であっても連れ子は相続の第1順位となり、法定相続人としての権利を持ちます。
たとえば、実の子1人と養子縁組した連れ子1人の場合、再婚相手は2分の1のままですが、残りの2分の1を実子と連れ子で均等に分けなければなりません。
実の子からすると「血のつながらない子と遺産を分けるのは納得できない」と不満を抱き、熟年再婚による相続トラブルに発展するケースも少なくありません。
そのため、あらかじめ遺言書の作成や話し合いが必要になるでしょう。
熟年再婚で起こりやすい4つの相続トラブルの内容

熟年再婚をすると、以下の4つの相続トラブルに発展する可能性が高いです。
- 実の子と再婚相手が相続の配分を巡り対立する
- 養子縁組をした連れ子と実の子が相続権を争う
- 遺言書がないことで、不公平な遺産分割となった
- 再婚相手が親の財産を生活費に流用し不信感が高まった
一つずつ解説します。
実の子と再婚相手が相続の配分を巡り対立する
熟年再婚では、実の子と再婚相手が相続の配分を巡って対立するケースが少なくありません。
法律上、再婚相手は婚姻期間に関係なく相続財産の2分の1を受け取る権利があり、その分、実の子の相続割合は減少するからです。
たとえば、再婚相手と実の子の間に関係性が築けていない場合、血縁のない相手と財産を分け合う不満と老後の生活を守りたい再婚相手の考えがぶつかり、感情的なトラブルに発展するケースがあります。
養子縁組をした連れ子と実の子が相続権を争う
養子縁組をした連れ子と実の子が相続で対立することも、熟年再婚をした家庭では起こりやすいトラブルのひとつです。
法律上、養子縁組をした連れ子は、実の子と同じ法定相続権を持ち、遺産を平等に分けなければなりません。
しかし、実の子からすると血のつながりのない人と財産を分けることへの強い不満から、相続の内容に納得できず、結果的に相続トラブルにつながる場合があります。
遺言書がないことで、不公平な相続内容となった
遺言書がないことで不公平な相続内容となり、相続トラブルへと発展する場合もあります。
実の親の遺産を相続する際、再婚相手には2分の1、残りを実の子や養子縁組をした連れ子が分け合うため、実の子の取り分が少なくなります。
また、相続に関する事前の準備が不十分で、再婚相手との関係が築けないまま相続を迎えると、相続の配分や内容に不公平さを感じ、相続トラブルに発展するケースも少なくありません。
再婚相手が親の財産を生活費に流用し不信感が高まった
再婚相手が親の財産を生活費に使い、不信感が高まりトラブルになるケースもよくあります。
実の子の中には、親の財産は家族で築いたものという思いが強い方もおり、血のつながらない再婚相手が自由に財産を使うことに、不満を抱く場合もあります。
特に、使い道がはっきりしない場合や事前に説明がない場合には「財産を食いつぶされているのでは」と疑いの目を向けてしまいがちです。
こうした不満や疑念が積もり、結果的に大きなトラブルへつながるケースもあります。
熟年再婚による相続トラブルを未然に防ぐ5つの対策


熟年再婚による相続トラブルは多いですが、方法次第では未然にトラブルを防ぐ事もできます。
熟年再婚による相続トラブルを防ぐには、以下の55つの方法がおすすめです。
- 実の親とあらかじめ再婚と相続について話し合う
- 公正証書(遺言書)を作成する
- 連れ子との養子縁組は慎重に判断する
- 生命保険を活用する
- 相続に詳しい専門家に早めに相談する
一つずつ解説します。
実の親とあらかじめ再婚と相続について話し合う
熟年再婚による相続トラブルを防ぐには、実の親とあらかじめ再婚や財産について話し合うことが大切です。
再婚によって家族のかたちが変わると、気持ちのすれ違いや思わぬ誤解が生じやすく、結果的に相続時のトラブルにつながることもあります。
そのため、実の親が再婚相手との関係や相続の考え方についてどのような考えや思いを持っているのか、早めに聞くことが必要です。
また、話し合うことにより、遺言書の作成や税理士・弁護士といった専門家への相談もしやすくなるメリットもあります。
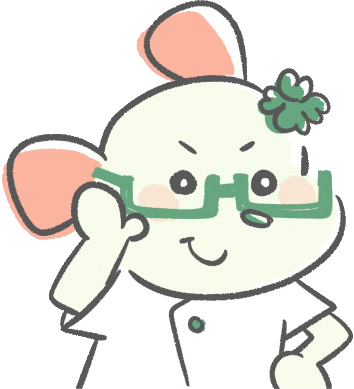
公正証書(遺言書)を作成する
再婚にともなう相続トラブルを防ぐには、公正証書遺言の作成も効果的です。
熟年再婚は、再婚相手と実の子との関係が築けないまま相続を迎えることが多く、財産の分け方をめぐって感情的な対立が生じやすくなります。
たとえば、実の親が「自宅は再婚相手に、預貯金は子どもに」と希望していても、遺言書がなければ意向が正しく伝わらず、残される家族の間で相続争いに発展する可能性があります。
そこで、あらかじめ公正証書遺言を作成すると、遺言の内容が法的に有効となり、公証役場で保管されます。
そのため、紛失・偽造などの心配がなく、実の親が希望した通りの内容で遺産が相続されます。
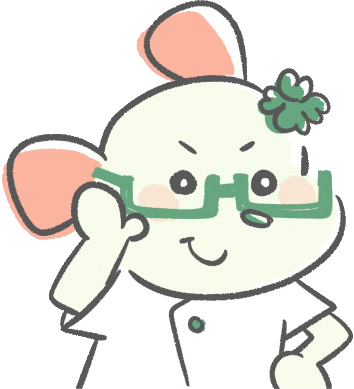
連れ子との養子縁組は慎重に判断する
連れ子との養子縁組は、熟年再婚における相続トラブルを招く可能性が高いため、慎重な判断が必要です。
養子縁組をすると、連れ子も法定相続人となり、実の子どもの相続配分が減り、家族間で感情的な対立が生まれやすくなります。
特に、成人した連れ子と実の親との関係性が薄い場合、その意義が問われることも少なくありません。
このようなトラブルを防ぐには、家族全員で十分に話し合い、養子縁組の法的な影響を理解したうえで判断しましょう。
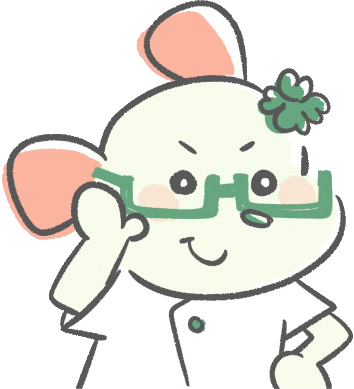
生命保険を活用する
熟年再婚による相続トラブルを防ぐために、生命保険を活用することも方法の一つです。
生命保険の死亡保険金は、相続の対象ではなく、あらかじめ指定した受取人がもらえるお金であるため、遺産相続で揉める前に、スムーズに受け取ることができます。
たとえば、再婚相手を受取人にすると、すぐに使えるお金を渡すことができ、実の子に「全部持っていかれた」と思わせずに済みます。
反対に、実の子を受取人にすれば、相続分が減ったことへの不満を和らげることもできます。
このように、生命保険を上手に活用すると、家族の気持ちに配慮しながら相続トラブルを防ぐことができるでしょう。
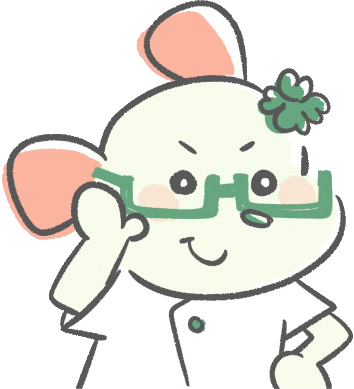
相続に詳しい専門家に早めに相談する
熟年再婚による相続トラブルを防ぐには、相続に詳しい専門家への相談も必要です。
再婚により相続人の構成が複雑になると、相続の配分や内容について、実の子と再婚相手、連れ子との間でトラブルが起きやすくなります。
たとえば、実の親が再婚相手に家を残したいという意向があったとしても、意向を示す証拠がなければ正確に伝わらず、残された家族の間でトラブルに発展することもあります。
そのため、以下の専門家に相談すると、状況に合った対策をとることができます。
- 弁護士:相続トラブル全般の法的なアドバイス、遺産分割協議・調停の対応など
- 司法書士:相続登記の手続き、遺言書の作成サポートなど
- 行政書士:公正証書遺言の作成サポート、相続関係説明図の作成など
- 税理士:相続税の計算や申告対策など
残された家族が相続で争わず済むように、あらかじめ専門家へ相談しましょう。
熟年再婚が介護施設の入所や老後の暮らしに与える影響とは?


熟年再婚は相続トラブルだけではなく、介護施設の入所を含めた老後の暮らしに影響を与える可能性があります。
こちらでは、熟年再婚における介護施設への入所や老後の暮らしにどのような影響があるのか解説します。
身元保証人やキーパーソンが変わりトラブルにつながる可能性がある
熟年再婚によって、介護施設の入所や老後の暮らしに関わる身元保証人やキーパーソンが再婚相手に変わる可能性があります。
身元保証人やキーパーソンが変わると、実の親の介護・医療などの重要な決定権が再婚相手に移り、実の子が直接関われないため注意が必要です。
例えば、介護の方針や財産管理の判断が再婚相手主導で進む場合、実の子の意向が反映されず、家族間で揉めるケースがあります。
このような問題を防ぐためには、再婚後に家族全員で実の親と再婚相手の意向を確認し、役割分担や連絡体制についてしっかり話し合うことが大切です。
介護施設の入所手続きや費用負担が新たなトラブルになる
介護施設の入所手続きや費用負担は、熟年再婚をした家庭で新たなトラブルになる可能性があります。
再婚相手と実の子の間で、介護施設の選択や費用負担に関する認識の違いによって、家族の間でトラブルになることも多いです。
たとえば、介護施設に求める希望や費用負担をめぐって再婚相手と実の子の間で意見が分かれてしまい、手続きがなかなか進まないケースも少なくありません。
そのため、事前に介護施設に求める希望や費用負担をはっきり決めるよう家族全員で話し合うことが必要です。
しかし、家族での話し合いがまとまらない場合、本サイトを運営している「近所のよしみ」への相談がおすすめです。
介護現場を経験したプロのスタッフが、ご希望に沿った介護施設を無料で紹介することができます。
さらに、入所後の看取りや葬儀、相続に関する相談にも対応しているため、気になる方はぜひ、以下のリンクから予約しましょう。
親の介護における役割を巡ってトラブルになる
熟年再婚した家庭では、親の介護を誰が担うかを巡って、再婚相手と実の子の間でトラブルに発展するケースがあります。
たとえば、実の子が「再婚相手が介護すべき」と考える一方、再婚相手は「実の子がやるべき」と主張し、責任の押し付け合いになることも少なくありません。
このようなトラブルを防ぐためには、介護が必要になる前に、家族全員で話し合いの場を持つことが必要です。
あらかじめ役割分担について、家族全員が合意することにより、いざ介護が必要となった際に慌てず済み、家族の関係悪化を防ぐことにもつながるでしょう。
まとめ
今回は熟年再婚による相続トラブルについて解説しました。
熟年再婚は実の親にとって大切な人生の再スタートです。
しかし、相続人の構成が複雑になることや遺言書などの準備不足などを理由に、実の子・再婚相手・連れ子との間で深刻な相続トラブルに発展するケースも少なくありません。
しかし、以下の5つの対策を講じることにより、相続トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
- 事前に再婚と相続について話し合う
- 公正証書遺言を作成する
- 養子縁組は慎重に判断する
- 生命保険を活用する
- 専門家へ相談する
また、介護や老後の生活についても、実の親と再婚相手の考えや希望をあらかじめ確認し、介護方針や役割分担、費用負担などはっきりしておくことがトラブル防止につながります。
「親が再婚したけれど、今後の相続や老後の生活が心配…」という方は、今回の記事を参考にし、早めの準備や家族との密なコミュニケーションを心がけましょう。














