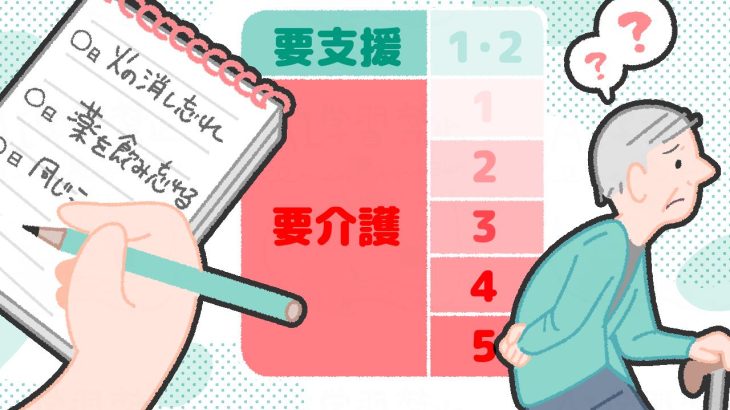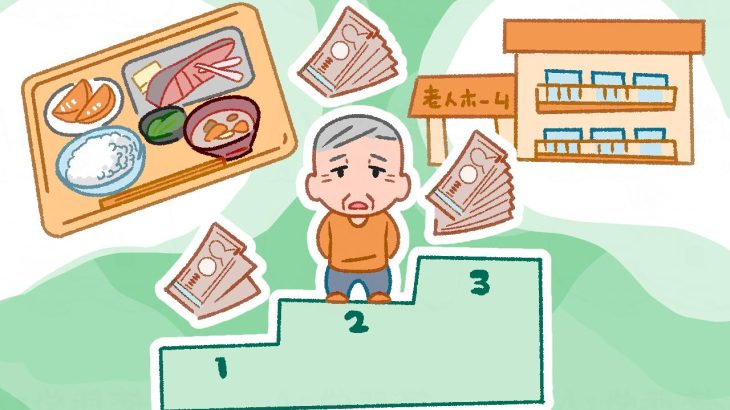看護師さんとデイサービス利用者の娘さんとの会話です。






難聴とは
音が聞こえにくい状態を難聴といいます。高齢者に多いのは加齢性難聴です。
加齢性難聴は、耳の中の音を感じる部位が障害されて起こります。
加齢性難聴の特徴
- 徐々に発症し、左右の耳でほぼ対称性にゆっくりと進行する
- 高い音から聞こえなくなる:玄関のチャイムや体温計の音、電子レンジの音など
- 小さい音は聞こえにくいが、大きい音はうるさく感じる
- ぼやけた、割れた、歪んだ音に聞こえる
- 早口の声がわかりにくくなる
初期症状
- 高い音が聞きとりにくい
- 子音が聞き取りにくい:特に「キ」「シ」「チ」などの母音が『イ行』のもの。「イチ」「キチ」「シチ」などが正確に聞き取れない
- 人混みや混み合った店内など、騒がしい場所での会話が聞き取りにくい
加齢性難聴の原因
耳の奥の内耳(ないじ)の内部にある有毛(ゆうもう)細胞の毛がダメージを受け、細胞数が減少することが主な原因です。
その他にも音を伝える神経経路の障害や、脳の認知機能の低下も影響している可能性があります。
難聴の程度分類
- 軽度難聴:小さな声や、にぎやかな場所での会話が聞き取りにくい
- 中等度難聴:普通の大きさの会話で聞き取りにくさや聞き間違いがある
- 高度難聴:非常に大きい声でないと聞き取れない。補聴器を装着しないと会話が聞こえない
- 重度難聴:耳元で話されても聞こえない。補聴器を装着しても聞き取れないことが多い


聞こえのセルフチェック
「近ごろ、よく聞こえないことがある」「家族からテレビや話し声が大きいと言われる」ということはありませんか。また、家族にこのような方はいませんか。
次のチェック項目は目安になるものですが、当てはまる項目が多い、増えてきたと感じたら耳鼻科で診てもらいましょう。
聞こえのチェック項目
本人より周囲の人が気づく場合もあります。ご家族とも一緒にやってみましょう。
- 会話をしている時に聞き返すことがよくある
- 後ろから呼びかけられると気づかないことがある
- 聞き間違いが多い
- 見えないところからの車の接近にまったく気づかないことがある
- 話し声が大きいと言われる
- 集会や会議など数人の会話でうまく聞き取れない
- 電子レンジの「チン」の音やドアのチャイムの音が聞こえにくい
- 相手の言ったことを推測で判断することがある
- 騒音の多い職場や大きくうるさい音のする場所で過ごすことが多い
- 家族にテレビやラジオの音量が大きいと言われることがよくある
判定結果
当てはまる数の合計で見ていきます。
- 0〜2個:現状は問題なし。実生活で困り事があれば耳鼻科受診をしましょう
- 3〜4個:耳鼻科で相談しましょう
- 5個以上:できるだけ早く耳鼻科を受診しましょう

認知症と難聴の関係
2017年の「国際アルツハイマー会議」でランセット国際委員会(グローバルヘルスに関する委員会)により、難聴は認知症の危険因子の1つに挙げられました。
この時、「予防できる要因の中で、難聴は認知症の最も大きな危険因子である」と指摘されています。
また、最近の国内外の研究で「難聴によって脳の萎縮や神経細胞の弱まりが進み、認知症の発症に大きく影響する」ことが分かってきました。
難聴になった場合の変化
コミュニケーションに支障をきたすことで認知症になる可能性が高くなるコミュニケーションに自信をなくし、消極的、引っ込み思案になる
- 会話がスムーズにできず、人との接触を避けるようになる
- 聞こえないことで「疎外感」「孤独感」「怒り」「苛立ち」「劣等感」などを抱き、周囲の言動に神経質になる
- 他の人の話を聞かず、自己主張してしまい攻撃的になる
- 難聴者の約半数にうつ傾向があり、社会的不適応となる
聞こえないことで周囲との関係性が悪くなり『難聴→孤独→うつ→認知症』の道筋が作られてしまいます。

耳と脳の関係
耳から入る情報は思考や情動に関わる
聞いた言葉の意味から「嬉しい」「悲しい」などさまざまな感情を抱きます。またその言葉への応答や行動を考えたりすることは脳にとって大きな刺激になります。
脳は使うほど活性化され、使わなければ衰えていくと言われています。聞こえの低下によって音や言葉が入らないことで、考えることや感じることが減り、それが脳の萎縮や機能低下につながると考えられています。
補聴器は認知症のリスクを軽減できる?
難聴による不便さは、早めに補聴器を使い出すことや日常生活の見直しで改善できる可能性があります。
- 補聴器をつけて適切な『聞こえ』を維持する
- 『聞こえ』を維持することでコミュニケーションを楽しみ、認知症の予防や発症を遅らせる可能性

聞こえを悪化させない生活
- 糖尿病、脂質異常症、肥満にならない生活をする:生活習慣病は内耳の血流を悪くし、難聴の進行につながる
- 質のいい睡眠をとる
- 自律神経を整える:ストレスを溜めない
- 必要以上の大きな音でテレビやラジオ、音楽を聞かない
- 定期的に運動をする:体の血流をよくする
- 禁煙:血管を収縮させてしまい、血流が悪くなる

まとめ
難聴は『微笑みの障害』と呼ばれます。
聞こえないことをもう一度聞き返すのが悪い、聞こえなかったことを知られたくないと微笑んで対応してしまう。
それが相手には「内容を理解して微笑んでいるんだろう」と思わせてしまい結果的に孤立につながることもあります。
個人差はありますが加齢性難聴で『聞こえ』が落ちるのは自然なことです。
自分は大丈夫だと思っていても周囲の人から指摘されることもあります。指摘された時をいいチャンスだと思い、聞こえのセルフチェックをしたり、耳鼻科を受診して相談してみましょう。